
作家・原田 マハさんがMIKIMOTOのために
書き下ろした連載です。
ここでしか出会えない
真珠にまつわるエッセイや
ストーリーをお楽しみください。
Vol.5
真夏の夜の夢
イギリスで口に含んだ日本酒は、
私を夢の世界に誘ってくれた。
前編
清橋夫人とは、とある老芸術家の功績を讃える小規模なレセプションで出会った。
その宴はロンドン郊外にあるコレクターの瀟洒な邸宅で開かれた。小規模とはいえ、品がよく、隅々まで気配りが行き届いた会であった。芸術家は日本人だったが、半世紀以上まえに渡英し、そのままロンドンで創作を続けている。ロイヤル・アカデミーの会員で、クイーンから「サー」の称号を授与されてもいる、いわゆる「名士」であった。
二十余名の参加者たちはイギリス人がほとんどで、日本人は数えるほどであった。その中に清橋夫人がいた。
そういう会では参加者が互いに知り合いを紹介し合って会話が始まるものだが、私にはこれといった知り合いがいなかった。直近に開催された芸術家の個展について短い展評を日本の美術雑誌に寄稿したのが彼の目に留まり、直々にお誘いを受けたのだ。
私は日本の大学で美術史の教鞭を執っていたが、一年間のサバティカルを得てロンドンに滞在中であった。その期間が終わり、来週には帰国する、というタイミングだった。
乾杯のあと、空のシャンパングラスを手に、私は手持ち無沙汰にその場に突っ立っていた。元来社交が苦手で、そういう場でどのように振る舞っていいかわからない。しかたなく、そんなことをするのは無粋の極みと承知していたが、麻のジャケットの内ポケットからスマートフォンを取り出してSNSをチェックした。日本で私の帰国を待つ妻からメッセージが入っていた。帰国まえにナショナル・ギャラリーに行って、来年のカレンダーを買ってきてね、忘れないで。私は苦笑した。ようやく七月になったばかりなのに、ずいぶんと気が早いものだ。妻も、ナショナル・ギャラリーも。
そこへ銀のトレイにいくつかショットグラスを載せたウェイターの青年が泳ぎ寄るようにやって来て、「どうぞ」と勧めてきた。「ありがとう」と私は、ジンかラムだろう、透明な液体が半分ほど入っているショットグラスを手に取ると、ひと息にそれをあおって、不意を突かれた。
豊穣で上品な甘味が口の中にふわりと広がり、やわらかく喉を下りていく。私が飲み干したのは日本酒だった。
思いがけず旧友に再会したような気持ちになった。私は先ほどのウェイターの青年に合図をして、もうひとつ、ショットグラスを手にした。今度は一気に飲み干さず、ちびりと飲んでみた。美味い。清水のように清冽な味わいである。
「お味はいかがですか」
ふと日本語で語りかけられて、私はそちらへ顔を向けた。
ひとりの日本人女性が佇んでいた。肩にかかるくらいの栗色の巻き髪、その内側で大粒のパールのピアスが輝いている。バーガンディーのサマードレスが立ち姿にしっとりと映え、二連につけられたパールネックレスが彼女の優美さを際立たせていた。ドレスと同じ色のくちびるに微笑を浮かべて、彼女は続けて私に尋ねた。
「その日本酒、お気に召されました?」
私はまた不意を突かれたが、「ええ、とても」と答えて微笑み返した。
「まさかイギリスでこんなに美味しい日本酒に出会うなんて……意外でした。意外なほど、美味しかった」
ショットグラスを少し持ち上げて見せて、
「もうお飲みになりましたか?」
私の問いに、彼女はいっそう微笑んだ。
「ええ。もう何度も」
それが清橋夫人との出会いであった。
甘露のごとき清冽なその酒は、彼女がイースト・ケンブリッジに開設した日本酒の醸造所で造られたものだと知らされた。
キングス・クロス駅から出発した電車は、小一時間ほどでケンブリッジ駅に到着した。
学生らしき若者たちがいっせいに降車する。車内には私だけが残された。
もう三十年以上まえのことだが、交換留学で一年間だけこの町の大学に通っていたことがある。だから、ひさしぶりに「Cambridge」と書かれた駅の看板を目にしてなんとなく胸が疼き、それが遠ざかっていくのが惜しまれた。この駅でもはや降りることは人生で二度とないのかもしれない。急に感傷的な思いが込み上げた。
そこから二十分ほどでイーリー駅に着いた。改札を抜けたときにはもうちっぽけな感傷は消え失せていた。私はすぐにタクシーに乗り、清橋夫人がショートメッセージで送ってくれた住所を運転手に告げた。
「お客さん、日本から?」
走り出してすぐ、バックミラー越しに運転手が気さくな口調で尋ねてきた。ええ、と私が答えると、
「サケを飲みにきたのかい? あそこの醸造所に」
「ええ、まあ。そうです」どうやらこのあたりでは有名な場所のようだ。
「美味しいんだろ? 日本のサケってのは」
「ええ。美味しいですよ。いまから行くところのは、特別に」
「だろうね。この土地で生まれた醸造酒なら、美味いに決まってる」
タクシーが到着したのは、信じ難いほど広大な庭のある屋敷だった。いや、庭と言うのは語弊がある。庭園、と言ってもまだ足りない。家畜はいないが牧場と言いたくなるほどの広さだった。
煉瓦造りの邸宅は典型的な十七世紀ジャコビアン様式である。正面の玄関ポーチのドアが開いて、清橋夫人が現れた。
「ようこそ」
夫人はにこやかに私を出迎えてくれた。たっぷりとした身幅の白いコットンのチュニックに白いパンツ姿である。襟元にはやはりパールのネックレスが揺れていた。
「ご帰国まえのお忙しいときに来てくださって」
「お招きありがとうございます」と私は言った。
「調子に乗ってほんとうに来てしまいました。そちらこそお忙しいでしょうに、ご迷惑では?」
「まさか。大歓迎ですよ。日本酒目当てに来てくださる方は、特に」
荷物を置いてからすぐ、「庭をご案内します」と誘われた。醸造所に直行するものと思い込んでいたので、まず庭を、という順番に私は感じ入った。
酒は神につながる神聖な飲み物なのである。飲酒に至るまでのプロセスに、庭を愛で心を安らげる体験を差し入れるなんて、すばらしくセンスがあるではないか。豊かな自然があふれるイギリスの田園地帯であるならば、なおのことだ。
原田 マハ
1962 年東京都生まれ。関西学院大学文学部日本文学科、早稲田大学第二文学部美術史科卒業。伊藤忠商事株式会社、森ビル森美術館設立準備室、ニューヨーク近代美術館への派遣を経て、2002年フリーのキュレーター、カルチャーライターとなる。2005年『カフーを待ちわびて』で第1回日本ラブストーリー大賞を受賞し、2006年作家デビュー。2012年『楽園のカンヴァス』で第25回山本周五郎賞を受賞。2017年『リーチ先生』で第36回新田次郎文学賞を受賞。




 Back
Back 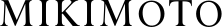



 「すべてが円くなるように」へ戻る
「すべてが円くなるように」へ戻る