
作家・原田 マハさんがMIKIMOTOのために
書き下ろした連載です。
ここでしか出会えない
真珠にまつわるエッセイや
ストーリーをお楽しみください。
Vol.5
真夏の夜の夢
イギリスで口に含んだ日本酒は、
私を夢の世界に誘ってくれた。
後編
前編はこちら夫人が日本でも有数の日本酒醸造会社のオーナー一族の一員であることを、すでに知らされていた。とあるきっかけがあって、彼女はあるとき、イギリスで醸造所を開こうと決心した。日本酒を通して日本の伝統・文化・精神性をイギリスの人々に、ひいては世界に伝えたい。アイデアはすばらしいが実現は難しいと、誰に相談しても同じように言われた。
が、彼女はあきらめなかった。長いプロセスとさまざまな苦労を乗り越え、また、数々の奇跡としか呼びようのない体験やよき出会いに励まされて、ようやく五年ほどまえ、この地にイギリス初の日本酒の醸造所を開設した──と、壮大な物語をあのレセプションで聞かされた。
私はその場ですぐに、一度伺ってみたいです、とお願いしてしまった。彼女が夢をかなえた場所を見てみたいと思ったからだが、それより何より、あまりにも彼女の酒が美味かったのだ。それが生まれた場所で飲んでみたい、と強く思った。
そしていま、私の目の前を清橋夫人が歩いている。白いチュニックが風をはらんでふわりと膨らむ。彼女が向かう先にとてつもない巨木が立っていた。私は、うわあ、と声を上げた。
「この木。私、この木に出会ってしまったの」
夫人は私のほうを振り向いて、笑顔を見せた。
なんの木だろうか、見たこともないスケールなのでわからなかったが、あっけに取られてしまった。四方いっぱいに広げられた枝には暗い赤紫の葉が生い茂り、枝中のほうぼうから小鳥のさえずりが聞こえる。茂りの下に入ると、とびきり居心地のいい大きな家の中に招き入れられたかのようだ。
夫人はどっしりと立つ木の幹に近づいていきながら、
「この土地に初めて案内されたとき、この木が私を招いているようで……こうやって近づいていって……」
幹に、ぴたりと抱きついた。私もまた、強い磁石に引き寄せられる砂鉄のように一気に近づくと、太い幹めがけて思い切り抱きついた。
子供じみた行為に違いなかったが、そんなことはどうでもよく、私は心地よく巨木に体を預けた。夫人がこの土地で新しいことを始めようと決めた、その心がこの木を通して伝わってくるような気がした。
それから夫人は庭園のあちこちで咲き乱れる花々や、イギリス人のガーデンデザイナーに依頼して造成した日本庭園や、小さな農園や果樹園を見せてくれ、最後に醸造所を案内してくれた。そこでできたばかりだという酒を銀のトレイに載せて、若い女性が現れた。
「長女の美和子です。酒造りは、この子の弟が担当しているんですけど。あいにく今日は留守にしていて」
夫人は日本とイギリスを忙しく行き来しているが、彼女の子供たちはこの場所で酒を造り、酒を守り、酒をふるまい、酒とともに暮らしていた。かつてこの地の領主が住んでいたという屋敷と美しい自然が残る庭園を整備して、訪問客を心尽くしでもてなしているのだった。
美和子さんははにかんだような微笑を浮かべて、透き通った液体が入ったグラスを差し出した。長い黒髪に夕陽が透けて、つややかな頬をきらめかせ、コットンの白いシャツの襟元に真珠のペンダントがのぞいている。少し灼けた肌に白く円いひと粒が涼しげに映えていた。さわやかな夏の夕風のような人である。
私は透き通ったグラスを手に取り、ひと口、ふくんでみた。ひと筋の清流が体の真ん中をすうっと通りすぎる。
「美味い」
ごく自然にそのひと言がこぼれ出た。
「ありがとうございます」
やはりごく自然に、母と娘は同時に言った。
「なんだか夢の中に迷い込んでしまったような気がしてきました」
もう何杯目だろうか、清水のごとき酒を味わいながら、私はそんなふうにつぶやいた。
庭のテーブルにキャンドルを灯し、母娘と夕食をともにしながら、私は夢心地だった。
黄昏が西の空へと遠ざかりつつあった。入れ替わりに明るい闇が近づいていた。私と向かい合って並んで座っている母娘の襟元の真珠をキャンドルの光が照らし出している。
「ぜんぶ、消えてなくなるのかな。明日になれば……日本へ帰れば」
自分の言葉に名残惜しさがにじんでいるのがわかった。帰りたくない、といつしか私は思っていた。時が止まればいいのにと。
ケンブリッジに通っていた頃、講義中に、開け放った窓から心地よい風が吹いてきて、手元の教科書のページを揺らした。ケネス・クラークの本の一ページ、何が書いてあったとか、手にしていたのは父が留学祝いに買ってくれたパーカーのボールペンだったとか、そんなことまで覚えている。
なんてことのない瞬間、しかし至福の瞬間だった。あのとき、私の心に浮かんだのは、時が止まればいいのに、という若く青い思いだった。
あのときと同じ気持ちが私の胸に広がっていた。
ふいにふたりの目を見て話せなくなった。私は、夫人の首回りを飾る真珠が揺らめくたびにキャンドルの光を弾くのをみつめていた。
「いいえ。消えてなくなったりしませんよ」
夫人の声がした。静かな、ピアノが奏でる和音のような声だった。
「この場所はずっとここにありますから。──またいらしてください」
私は目を上げた。
大樹がシルエットになって私たちを見守るように佇んでいる。
夢かもしれない。けれど、その刹那、たしかに時が止まった。
後編は近日公開
原田 マハ
1962 年東京都生まれ。関西学院大学文学部日本文学科、早稲田大学第二文学部美術史科卒業。伊藤忠商事株式会社、森ビル森美術館設立準備室、ニューヨーク近代美術館への派遣を経て、2002年フリーのキュレーター、カルチャーライターとなる。2005年『カフーを待ちわびて』で第1回日本ラブストーリー大賞を受賞し、2006年作家デビュー。2012年『楽園のカンヴァス』で第25回山本周五郎賞を受賞。2017年『リーチ先生』で第36回新田次郎文学賞を受賞。




 Back
Back 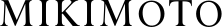



 「すべてが円くなるように」へ戻る
「すべてが円くなるように」へ戻る