
作家・原田 マハさんがMIKIMOTOのために
書き下ろした連載です。
ここでしか出会えない
真珠にまつわるエッセイや
ストーリーをお楽しみください。
Vol.4
庭の朝露
母を喪った真彌は久しぶりに京の実家に足を踏み入れた。
きれいさっぱり片付けたはずの家に、母の忘れ物があるという。
前編
あれはいつのことだったか、京都にある実家の中庭で、もうずいぶん長いこと耳にしなかった母の京言葉が思いがけず聞こえてきたことがある。
初夏だった。小さな庭に植え込まれた青紅葉や隠れ蓑、千両などが葉陰の緑を色濃くしていた。その中へ、ふいに下駄も履かず素足で降り立った母が、蹲に向かって何かつぶやいているのが、縁側にいた私の耳に聞こえてきたのである。
――そうどすか、お苔さんが生しおしたか、あんさんもえらいこと古うなりおしたな……。
と、そんなふうに語りかけていた。
どうしてそんなことを覚えているかというと、めったに中庭に降りたりしなかった母がそこに降り立って、しかも素足で、そして苔むした蹲に向かって語りかけているという異様さと、浴衣の裾から伸びた細く白い足首の艶かしさと、その頃にはもうあまり使わなくなっていた京言葉の歌うような滑らかさが相まって、記憶に留まることになったのだと思う。
そのとき自分が母に声をかけたのか、かけなかったのかは覚えていない。ただ、エアコンをつけずには過ごせない京の夏の盛りのまえ、清涼な風が吹き抜ける古い町家の室内で、まるで娘時代に戻ったかのように無邪気な母が庭へ降りて蹲に語りかける、その刹那を見守っていた。誰もいない美術館の展示室、ガラスケースの中に掛けられた一幅の軸絵を眺める感覚だった。
その後しばらくして、母は入院した。
階段で足を滑らせ転倒して骨折したからだったが、いかに住みづらい町家であろうとも、またいかに歳を取ろうとも、生まれ育った家の階段――急傾斜の「ハコカイダン」――を踏み外すなど、私も母自身もついぞ想像しなかったのが裏目に出た。
父に先立たれてから十年近く、母は独居を続けてきた。使いづらく面倒くさい町家暮らしをやめなかった理由はなんだろう。
この家以外で暮らすんなん考えられへんわと、母は常々言っていた。新しい家に建て替えたら? リフォームしたら? と私はいくたびも提案したのだが、がんとして受けつけなかった。
それで結局、入院の憂き目に遭ってしまった。その後、家に戻ることなく高齢者施設に入所することになった。
少しまえから意味不明なことを口走ったり、物の名前が言えなくなったり、母が少しずつ現実世界から遠ざかっていくのがわかった。孫娘が面会に行くと、真彌ちゃん、会いにきてくれたん? とうれしそうに私の名前を呼んだそうである。おばあちゃま、なんだか可愛かったよと、娘は私に電話してきてそんなふうに言った。
そうして先ごろ、母は静かに旅立っていった。
ひとり娘の私に、古い町家が遺された。
築年数不明、そんなもん付けるんいややと拒否する母を説得して無理やり私が設置したエアコンだけが真新しい。
ミセ、ダイドコ、オク、ハナレ、ハシリニワ、ヒブクロ、ニワ。京町家らしい風情をそのまま残した家。
時が止まった家。
そこかしこに母の気配が漂う家。母のまなざしそのもののような家。
通りに面した格子戸の窓を開け、中庭が見えるガラス戸を開け放つと、清々しい風がすうっと通り抜けていった。
「ええ風が通りますねえ。これがほんまに町家のええとこですわ」
銀行から派遣された不動産鑑定士の男性が、額に浮かんだ玉の汗をハンカチで拭ってそう言った。私は笑って、
「いい季節はいいんですけど、真夏は、さすがに……真冬も底冷えしますし」
とかく京都の町家は暮らしづらい……と言いかけて、やめておいた。売却すると決めたのだから、余計なことは口にしないほうがいい。
「ええお庭ですね。ええ景色を作ったはる。敷石もええ感じに苔むして……蹲も、ええお姿やなあ」
縁側に佇んで彼が言った。素直な口調だった。私は微笑した。ミセからダイドコを通ってオクへと案内し、ニワを見せるまでに、彼は「良い」という形容詞を繰り返し使ってこの古家を褒めてくれた。そして、ここまで状態のいい町家は最近では珍しい、と初感を述べた。
「買い手はつきますでしょうか」
そう尋ねると、「私は売買の方は専門外ですんで」と断りつつも、
「最近は、古民家をリノベーションしてレストランや宿に転用しはる人もぎょうさんいてるようやし、町家を欲しがる外国人も増えとるそうですからね」
きっとすぐにみつかるんと違いますか、と楽観的な意見を述べた。
ひと通り家の中を案内して、事務的な会話を交わしたあと、ミセ先まで見送りに出た。
鑑定士は土間に揃えられた靴を履いてから、こちらに向き合うと、
「ええ物件を拝見させてもろうてよかったです。ほな、失礼いたします」
ていねいに頭を下げて帰っていった。
一階と二階、開け放った窓を閉めて回った。京町家は正面に出入り口と窓があり、「うなぎの寝床」と呼ばれるそのままに、奥に向かって長細く、中庭や坪庭が配されている。ハシリニワと呼ばれる長い土間には炊事場があり、その上は二階まで吹き抜けになっている。正面と奥の窓を開けると、家の中に風の通り道ができる。京都の家は夏仕様だと言われるが、実際その通りである。
京都市街は盆地の底にある。だから夏は熱がこもってうだるように暑く、冬はその逆でしんしんと寒い。その昔、疫病が大流行したのもそんな土地柄だからだろう。疫病退散を祈願して祇園祭が始まり、町家の軒瓦の上には疫病退治の守り神「鍾馗さん」が鎮座するようになった。
夏には襖を外して簾を垂らし、冬には手火鉢に炭を熾して、面倒なことに折り合いをつけ、暮らしづらさに工夫を重ねて、この町の人は生き抜いてきたのだ。
母もその中のひとりだった。西陣の組紐商の家に生まれ、職人頭だった父を婿養子に迎えて、伝統の灯を絶やさずに継いできた。しかし、父の逝去後、後継者がなく、そこで家業は仕舞いとなった。それから母は独りでつましい暮らしを営み、誰に迷惑をかけるでもなく、ひっそりと人生の幕引きをして、旅立っていった。
親元を離れて東京の大学に進学した私は、東京で就職し、家庭を持った。母と同じだったのは、ひとり娘を授かったことと、夫に先立たれたこと。それ以外は母とはまったく違う道を歩んできた。
新卒で入社した企業に勤続三十余年、娘の真琴が大学を卒業して社会人になるまでどうにか見守ることができた。働きながらの子育ては苦労も多かったが、喉元過ぎれば熱さを忘れる、というのは本当だ。社会人五年目となったこの春、真琴に結婚相手を紹介された。ここまで頑張ってきてよかったなと、ようやく思えたのはそのときだった。
真琴は、おばあちゃまにもちゃんと伝えたいんだと言って、母のいる施設へ婚約者を連れて会いに行ってくれた。祖母と孫娘の対面は、それが最後となった。
縁側のガラス戸を閉め、鍵をかける。
「ええお姿」だとさっき褒められた蹲が庭の片隅、庇の下にうずくまっている。ガラス窓越しに覗き込むと、紅葉の枯れ葉が一枚、かすかな朱色を残して、ひからびた水鉢の底で静まり返っていた。
原田 マハ
1962 年東京都生まれ。関西学院大学文学部日本文学科、早稲田大学第二文学部美術史科卒業。伊藤忠商事株式会社、森ビル森美術館設立準備室、ニューヨーク近代美術館への派遣を経て、2002年フリーのキュレーター、カルチャーライターとなる。2005年『カフーを待ちわびて』で第1回日本ラブストーリー大賞を受賞し、2006年作家デビュー。2012年『楽園のカンヴァス』で第25回山本周五郎賞を受賞。2017年『リーチ先生』で第36回新田次郎文学賞を受賞。




 Back
Back 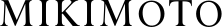




 「すべてが円くなるように」へ戻る
「すべてが円くなるように」へ戻る