
作家・原田 マハさんがMIKIMOTOのために
書き下ろした連載です。
ここでしか出会えない
真珠にまつわるエッセイや
ストーリーをお楽しみください。
Vol.4
庭の朝露
母を喪った真彌は久しぶりに京の実家に足を踏み入れた。
きれいさっぱり片付けたはずの家に、母の忘れ物があるという。
後編
前編はこちら強い風を伴ってひと晩降り続いた雨は、ホテルを出る頃にはすっかり上がって、京都御所の真上には青空が広がっていた。
ひと足遅れて真琴が京都へやって来た。一緒に京都にいるのはひさしぶりだし、せっかくだからと、ホテル近くの御所内を散策した。
烏丸通に面した蛤御門から入り、御所西の路を上がっていく。葉桜や青紅葉のみずみずしい緑陰の中を母娘で肩を並べて歩くのは、なんとも言えない幸福感を私にもたらしてくれた。
「いい気持ち。お天気になってよかったね」
真琴は若鮎のようにすんなりした手を目の前にかざして空を仰いだ。葉陰越しの陽光が、その左手の薬指に留まった真珠のリングをやわらかくきらめかせている。婚約指輪として清らかな真珠のリングを贈った娘のパートナーに、私は好感を持った。
「仕事、大丈夫だったの? 休んできたんでしょ?」
私が実家の売却を進めていることを、真琴は反対こそしなかったが、幼い頃にたびたび遊びに行ったあの古い家にもう会えないのはなんだかさびしい、人手に渡るまえに見納めたいと、駆けつけたのだった。
「うん、大丈夫。大事なことだから」
真琴が答えた。すなおな響きの声だった。
彼女が小学二年生の頃、葵祭の見物のために家族みんなで御所へ来たことがある。京都の実家のとなりに住んでいた仲良しのさやちゃんが、斎王代の十二単の裳裾を持ってお供をする童女に扮して行列に加っていた。白粉を塗り口紅をさして、目の醒めるほどあでやかな着物を着たさやちゃんがうらやましくて仕方がなかった、と真琴は思い出話をした。そして、
「あのときは、おばあちゃまもおじいちゃまも、お父さんもいたね」
しみじみと言った。
斎王代とお供の童女たちのまぼろしが、ほんの一瞬、私たちがそぞろ歩く路の先に現れて、消えた。
表通りに面した格子戸の窓と中庭のガラス戸を開け放って、風の通り道を作る。
「ああ、いい風」
大きく息を吸い込んで、真琴が言った。
「――なつかしい。おばあちゃまのうちのにおい」
私は微笑んだ。長い時間が熟成した歴史のにおい、とでもいうのだろうか。この家には、民藝館の展示室のような空気感があるのだ。真琴は家の中をぐるりと見回して、
「すごい。見事に空っぽ」と感嘆した。
「でしょう」と私は応えた。
「入院するまえから、おばあちゃま、少しずつ身辺整理してたみたい。亡くなったあと、大きい家具なんかはリサイクル業者に引き取ってもらったんだけどね。おばあちゃまの身の回りのこまごましたものは、ほとんど片付けずに済んだよ。ほんとうに、きれいさっぱり……」
きれいさっぱりいなくなったーーと言いかけて、やめた。
母は、もういない。
胸の奥で水泡のようなさびしさがぷつんと弾けた。
中庭の植栽は朝方降った雨露を葉に留めてきらめかせている。縁側に腰掛けて、真琴は両足を濡れた踏み石の上に預けた。桜色のペディキュアをした素足が陽だまりの中に並んだ様子は、幼い頃、同じ場所で白いソックスの両足をぶらぶらさせていたのを私に思い出させた。
「……おばあちゃま、何を忘れてきたのかな」
ふと、真琴がつぶやいた。え? と私は我に返って、
「忘れてきた、って?」
真琴は、うん、とうなずいた。
「最後に会いに行ったとき、おばあちゃまが言ってたの、急に思い出した。うちに忘れ物をしてきた、取りに行ってほしい……って」
孫娘を私だと勘違いした母は、真琴の手を握って言ったそうだ。大事なもん忘れてきてしもうた、真彌ちゃん、取ってきてくれへんかーーと。
「ね、お母さん。ちゃんとチェックした? 箪笥の中とか、押し入れの中とか」
私は笑って答えた。
「もちろん。何にもなかったよ。きれいさっぱり」
「そうかあ。そうだよね。きれい、さっぱりね」
真琴も笑って、立ち上がった。
――と、踏み石の横にある蹲を真上からのぞき込んで、
「――あ」
小さく声を上げた。
そのままじっとみつめている。私も縁側から蹲をのぞき込んだ。
覚えている。昨日見たときは紅葉の枯れ葉が干からびた水鉢の底で静まり返っていた。昨夜の風雨がそれをどこかへ吹き飛ばしてしまったのだろう、そこに枯れ葉はなかった。その代わり、に小さく光る何かがあった。真琴の指先が、それをそっとつまみ上げた。
あ……。
私も、思わず声を上げた。
真珠の指輪だった。
覚えている。かつて、母の薬指に留まっていた指輪。いつかは覚えていないけれど、いつのまにかそこから消えていた指輪。
――ああ、そうだ。
父が旅立ったあと、ひっそりと姿を隠したのだ。――この蹲の水鉢の底に。
そうだったんだーー。
真琴は、何も言わずに母の指輪を私の手のひらに載せた。彼女の目には朝露のような涙が浮かんでいた。
私は、手のひらの中に真珠のひと粒をそっと包み込んだ。
やわらかな温もり。母の、ぬくもりだった。
後編は近日公開
原田 マハ
1962 年東京都生まれ。関西学院大学文学部日本文学科、早稲田大学第二文学部美術史科卒業。伊藤忠商事株式会社、森ビル森美術館設立準備室、ニューヨーク近代美術館への派遣を経て、2002年フリーのキュレーター、カルチャーライターとなる。2005年『カフーを待ちわびて』で第1回日本ラブストーリー大賞を受賞し、2006年作家デビュー。2012年『楽園のカンヴァス』で第25回山本周五郎賞を受賞。2017年『リーチ先生』で第36回新田次郎文学賞を受賞。




 Back
Back 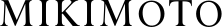




 「すべてが円くなるように」へ戻る
「すべてが円くなるように」へ戻る