
作家・原田 マハさんがMIKIMOTOのために
書き下ろした連載です。
ここでしか出会えない
真珠にまつわるエッセイや
ストーリーをお楽しみください。
Vol.6
ユーレイカ
装いたいように装い、
生きたいように生きることの
美しさを描く、極上の掌編。
ベスはいつもたくさんの友人に囲まれ、ハンサムなボーイフレンドまでいた。
彼女に憧れた私は、教室の片隅でスタイル画をノートに写し取るようになる。
中編
前編はこちらある日のこと、ゼミの教授が招いた著名な知識人の講義があるとのことで、いつも閑古鳥が鳴いている教室が満席になった。
私は早めに行っていつもの定位置に座っていた。授業開始から少し遅れてベスが入ってきた。たまたま私の隣の席がひとつ空いているのをみつけた彼女は、そこへやって来て座った。
私と目が合うと、彼女は微笑みかけて、(すごい人だね)とささやいた。私はどきっとして、あわてて落書きで埋め尽くされているノートを隠した。
しばらくして、彼女は自分のノートに何か書き付け、私の方へそれを滑らせて見せた。
〈なんか描いてるの? よかったら見せて〉
私の胸が、またどきりと波打った。私が「何か描いてる」のを彼女が素早くみつけてくれたことが意外だった。
描かれているのはぜんぶ、彼女のルック。どうしよう、と戸惑ったが、まさか自分だとは思わないだろう。私は、〈ヘタだけど……〉と走り書きして、思い切ってベスにノートを渡した。
それもまた意外だったが、ベスは私のノートを一ページ一ページ、ていねいにめくってじっくり眺めた。私は緊張しながら長いまつ毛の横顔を盗み見た。頬杖をついた手。ほっそりした指には小さなひと粒真珠のリングが品よく留まっている。耳たぶぎりぎりの真珠のピアスと呼応して、私の憧れを掻き立てるのに十分な輝きを放っていた。
ややあって、彼女は私のノートにまた何か書きつけ、そっと私の方へ滑らせた。その走り書きを目にして、これで三度目、私の胸の中で、ぽん、と大きく何かが弾けた。
〈これ、全部私? なんだかうれしい。ありがとう〉
永遠に交わらないと思い込んでいたベスと私の時間が、突然、交錯したのはそのときだった。
ベスが毎週末通っているというその店は、下北沢の外れの住宅街の一角にあった。
邪宗門──という不思議な名前の喫茶店。明治生まれの詩人、北原白秋の詩集のタイトルと同じ名前だと知ったのは、もっとずっとあとになってからのことだ。
──うちの近所にすごく雰囲気のある喫茶店があるの、きっと好きだと思うから、よかったら行かない? と誘われた。
ノートを見せた日から、私とベスの距離は少しずつ縮まっていった。とはいえ、どこかへ遊びに行くとか、一緒にランチをするとか、そういうのではなく、講義のとき、ベスは決まって私の近くの席に座って、また何か描いた? 見せてくれる? と声をかけられる程度だったのだが、それでも大きな変化だった。
私にとってベスはオードリー・ヘップバーンかブルック・シールズのような存在で、その頃にはそんな言葉は知らなかったが、言ってみれば私の「ファッション・アイコン」だった。アイコン本人に彼女のスタイル画のようなものを見せるのは、なんとも気恥ずかしく、同時に背筋が伸びることでもあった。
私はアルバイト代からお金を捻出して「スタイル画入門」なるものを何冊か買い、本格的にファッション画を描き始めた。ベスのルック中心だったが、自分で「こんなドレスにこんなコートを合わせて」と、勝手にデザインした服をスラリとした女性像にまとわせた。こんな服、私持ってたっけ? とベスに聞かれて冷や汗をかくこともあった。
私のノートに見入るベスの表情はいつも真剣で、凜々と音が聞こえてくるほど涼やかだった。そして私にノートを返すときには、いいね、とっても、と、今度はほころびた野ばらのような笑顔を見せてくれるのだった。
ベスが私を〈邪宗門〉に誘ってくれたのには理由があった。そこに行くといつもある女性が同じ席に座っているのだけど、その人が自分の憧れの人で、彼女のルックが最高だから私に見せたい、そして彼女のスタイル画を描いてみてほしい──と頼まれたのだ。
ベス以外の女性をモデルにしてスタイル画を描くなんて、そんなことできるだろうかと迷ったが、ベスが自分の行きつけの店に誘ってくれたのは嬉しかったし、何よりベスの憧れの人を見てみたいという強い好奇心が私を動かした。
私は食堂のバイトのシフトを別のバイト生に代わってもらって、ベスとのお出かけに臨んだ。自分のいちばんお気に入りのコーディネイト──黒いクルーネックのセーターの裾から白いシャツをちらっと覗かせて、クロップド丈のデニム、素足にローファー──で出かけていった。ベスは束ねた髪にシルクのスカーフを巻き、黒いタートルネックのセーターの襟元にベビーパールのネックレスを小粋につけて、ファッション雑誌のパリジェンヌ特集から抜け出してきたようなルックだった。おしゃれな女子大生ふたり連れを気取って喫茶店に入っていくのは、なんとも言えない快感だった。
原田 マハ
1962 年東京都生まれ。関西学院大学文学部日本文学科、早稲田大学第二文学部美術史科卒業。伊藤忠商事株式会社、森ビル森美術館設立準備室、ニューヨーク近代美術館への派遣を経て、2002年フリーのキュレーター、カルチャーライターとなる。2005年『カフーを待ちわびて』で第1回日本ラブストーリー大賞を受賞し、2006年作家デビュー。2012年『楽園のカンヴァス』で第25回山本周五郎賞を受賞。2017年『リーチ先生』で第36回新田次郎文学賞を受賞。




 Back
Back 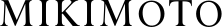



 「すべてが円くなるように」へ戻る
「すべてが円くなるように」へ戻る